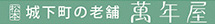4月, 2021年
最後の仕事
最後の仕事。踏み込みです。

タンクに入れた味噌の空気を抜くために踏み込んで行きます。
味噌の上にビニールを敷き40センチ四方のウレタンの板に乗って踏み込んでいきます。
以前、子供がやりたいと言ったのですが、体重が足りずに踏み込んでも全く沈まなかったので、これは大人の仕事になりました。
ここまで終わると、本当にほっとします。
後は秋まで美味しくなるのを待つだけ。
微生物よ、後は任せたぞ!
混ぜて仕込む
砕いた味噌玉を、塩と麹と水と混ぜてタンクに仕込みます。

下の写真は、砕いた味噌玉です。あんなに大きかった味噌玉が、このように小さくして、仕込むのですよ。

ちなみに、この味噌玉を砕く作業が終わると、主人はいつも肩が痛いと言ってます。機械に入れる時もかなり力を入れて、ガリガリ、ゴリゴリ砕いていく感じですね。
昔の人は、これを手で砕いていたので、大変な作業だったと思います。よく家庭で作っていたなぁと感心しますね。
信州では戦後まで味噌玉作りの味噌は家庭でも作っていた仕込みです。高度成長の頃から急激に作る人がいなくなりました
この時に、麹の割合を変えて味噌の種類を増やします。
萬年屋では、
5割麹 中辛(本店のみ販売)
8割麹 神撰
10割麹 豊麗
15割麹 極味
麹の割合が多いほど甘みと旨みが増し、少ないとキリッと辛口になります。
元は同じ味噌玉なのに、味の変化が面白いですね
味噌玉を砕く
味噌玉を砕きます。

きれいに現れた味噌玉を、チョッパーと呼ばれる機械で砕いていきます。
外側はスイカの皮くらい硬くなっているので、
★包丁で切るとか
★マッシャーで潰すとか言うレベルの硬さではありません😅
昔の人は、臼と杵でついたと言ってます。まるで餅つきですよね。
お客様の中では、年取って味噌玉を作れなくなったとおっしゃる方がいます。
味噌玉を洗ったり、砕いたりするのが重労働だからですよね。
これ全部、手仕事。
萬年屋の味噌玉に企業秘密はありますかと聞かれるのですが、ありません😄手間と工場の微生物だけです。
味噌玉の味噌は信州の方言で、「ずく=やる気、根気、元気」があれば作れます😝
挑戦してみますか!?
きれいになりました!
カビもあめもなくなり、きれいになった味噌玉。

ここまでくると、口に入れても良さそうな見た目になりましたね。
カビが生えたところを見ると、びっくりする人もかなりいたのではないかと思います😬
昔の人は、カビが生えたものを食べる勇気があったんですね。すごい❤️
私にはあんなカビが生えた大豆、食べたくないですもの😅
ゴシゴシ洗う
味噌玉を洗います。
本当にゴシゴシと、たわしでカビを落としていきます。

崩れないのかと心配される方も多いですが、鏡餅ほどの硬さになっておりますので、崩れてなくなる事はありません😄
味噌玉を洗います
味噌玉洗うのはこんな感じ。

乾燥してひび割れた所に生えたカビも、ヘラで掻き出します
かなりめんどくさい作業です。こういう手間のいる作業が大変で、一般家庭では作らなくなったのだろうなと思います。
カビのまま仕込んでいたと言う人もいますが、かなりかび臭く強烈な味噌になると思います。
一口だけ食べてみたいような、みたくないような…😅
味噌玉をふやかす
・
味噌玉は洗います。

味噌玉についたカビは体に害は無いのですが、
カビのまま仕込むとカビ臭い味噌になるので、いちど水に漬けてふやかし、カビを洗い流します。
鏡餅くらい硬くなっているので、水の中に1時間ほど入れても全く崩れないのですよ❗️
ある意味 美しい
味噌玉に生えたカビ。

ケカビと言う種類で、中国の発酵食品に多いカビです。
ここまでくると、ある意味芸術的に美しいカビですね。
流れるあめ

味噌玉からあめが流出すように出てます。
中で微生物が活発に動いて、大豆がどんどん熟成しています!
いつ見ても、自然の力はすごいなと思います。
食物なのに、微生物の働きで目に見えて動いているのがわかるのが面白い。
静かな時に、工場に行くと「ぷちぷちぷち」と言う音がします。
まさに発酵中です!
熟成が進む❗️
味噌玉は気温が高いと、一気に熟成が進みます。
全体をみると、こんな感じ。それぞれにあめが出てますねー❗️