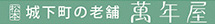商品のご紹介
味噌の仕込み 〜大豆を蒸す〜
3月下旬から味噌の仕込みが始まっています。今年は色々と忙しく、随時アップできなかったので、仕込の前半をまとめてご紹介します。
まずは大豆を洗って蒸大豆にします。 一度に540kgの大豆を仕込みますが、水を含むと2倍になるので、釜の中には1トン以上の大豆が蒸しあがってきます。

水分を含むと大豆は2倍になるので、蒸しあがると釜の8分目くらいまでになります。
糀の仕込み その3
糀は室ぶたに入れ、ふたをした状態でもう一晩 発酵させます。3日目は室だしです。一つ一つふたを開け、室から出していきます。 
糀が上手にできたかが、ドキドキの瞬間です。米の水分量や気温・湿度、室の温度加減等、毎回条件が違うので何度作っても、ふたを開けるまでは心配です。
今回も良い糀が出来て、ほっとしました。あとは室から出して、並べます
糀の仕込み その1
さあ!! 春は仕込みの季節です。
まずは売り糀のしこみから始まりました。信州はまだまだ各家庭で味噌を仕込む風習が残っています。それに必要なのが糀。仕込糀の前にお客様用の売り糀から仕込み始めました。
初日は米を洗って水に浸しておきます。
写真は2日目。蒸した米に麹菌をまぶす作業です。大釜から米をベルトコンベアーに入れて冷まし、手で混ぜながら製麹器に平らになるように入れていきます。
この作業は米の温度が非常に大切。ベルトコンベアーにいれる米の量を調節しながら、手の感覚だけで丁度良い熱さになるように仕込んでいきます。
見習い女将もこの仕事をはじめて3年目。少しずつ様になってきているでしょうか?!
まだまだ教わりながらの仕事ですが、物を作るというのは楽しい作業ですね。
味噌の仕込み
味噌の仕込みも来週(3月最終週)から始まります。
よく、テレビや雑誌のの取材で仕込の様子を撮りたいとご連絡いただくのですが、味噌玉造りの味噌は一年に一度しか仕込が出来ません。
取材の方、今がチャンスですよ〜。
仕込をご覧になりたい方は、ご連絡下さいね。時間が合えばご案内出来るかもしれません(写真は去年の仕込みの様子)
赤かぶが真っ赤に漬け上がりました
こうじが出来上がりました
糀の仕込みが終わりました。室での作業は高温多湿のため、カメラが曇ってしまい撮れずに残念。次回撮るように何か考えます。
今回出来上がった糀は、とてもとても上手にできました。お米一粒一粒にまで麹菌がついて、胞子がふわふわのとても良い糀です。
室ふた1枚は1升=1.5kgです。一升桝で量って一枚一枚入れていくのですよ。写真を見ればわかりますが、普通の桝と1升桝と比べてくださいね。
1kg入り900円、500g入り450円ですので、ご購入されたい方はメールまたはお電話下さい。
info@mannenya-nejp.check-xserver.jp ℡0263-32-1044
赤かぶ漬
ようやく赤かぶの収穫期なり、手に入りました。赤かぶは一年に一度しか出回らないので、沢庵漬けと重なるこの時期が勝負です。赤かぶを一つ一つ手で洗い、傷みそうなところは包丁で取り除きます。葉っぱの根本に土がこびり付いていたり、蕪に土がめり込んでいたり、これがなかなか大変な作業で、半日洗うと体中が痛くなります。沢庵漬けている方が楽かなぁ。。。
赤かぶを一度塩漬けにすると、色が抜けるのですよ。初めて漬けたときは、色が抜けてしまった・・・・とギョッとしましたが、これが不思議。酢に漬けると赤く鮮やかに色が復活するのです。まるで手品みたいですよ。次回は赤く染まった赤かぶの写真をご紹介しますね。
沢庵作り その3
干した大根を漬けこみます。沢庵の重さを量り、それに合わせて、糠・塩・柿の皮・なすの葉を入れて漬けます。
なすの葉はこの時期になると、八百屋さんで売ってるので買ってきます。柿の皮は売ってもいるのですが・・・家に柿の木があるので、それを取ってせっせと食べて干しています。たくあん仕込む前に柿を食べなくっちゃ!!という、状況です(笑)
2月頃になると食べられます〜。今ある沢庵は年内くらいでなくなりそうなので、しばらく品切れです。すみません。
沢庵つくり その2 大根干し
沢庵用の大根を干しました。今年は一度に大根が入荷したので、大変でしたが、見応えのある風景となりました。今年は赤かぶ漬けも同時期に重なり、毎日、漬物造りに追われていました。もう少し早くアップできればよかったのですが・・・
大根は干すときは井桁に組んで天井ぎりぎりまで入れるのですが、乾いてくると、かさが減り次第に上の方がスカスカになってきます。それもご覧ください
今年は天気も良く風もあったので、1週間ほどで乾きました。2週間近くかかる年もあるのですよ。
沢庵作り
沢庵用の堅大根・地大根と呼ばれる、短い大根を干しています。
今年は2300本程作る予定です。
沢庵を作る頃になると、冬が近づいてきているなぁと感じます。
子供達もこのお手伝いは大好きで、娘も学校から走って帰ってくるほどです。